保育士の給料が上がる!?政府提示の給与引き上げニュースまとめ(2016/09/30)
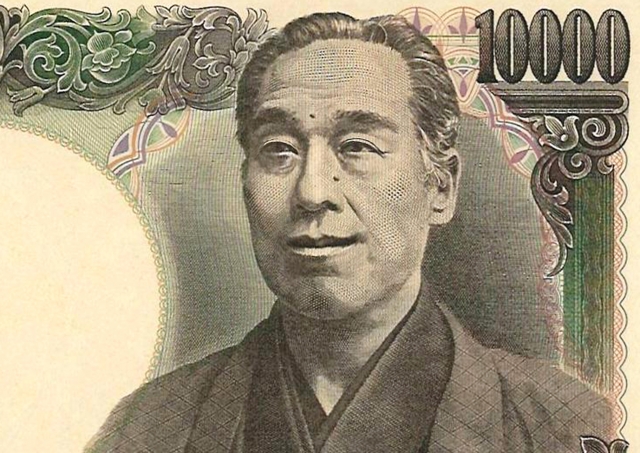
今春、政府より保育士の給与引き上げが表明され、同案に注目が集まっている一方、実施の可否や給与増額の妥当性など、さまざまな議論が巻き起こっています。
また、各自治体でも保育士の処遇改善や待機児童の減少に向けた取り組みを表明するなど、保育に関わる問題は今、急速に改善の方向へ向かっています。しかしながら、これらの問題は容易に解決できるものではなく、各案はあくまでも方針にすぎません。
今回は、今注目されている保育士の給与引き上げ問題について、現状の平均年収や待機児童問題などを交えながら詳しくお話しいたします。
⇒看護師と比べても安いの?看護師の給料明細投稿サイト「みんなの給料・年収」
1、人材不足の主な原因となる低給与問題
平成26年度の厚生労働省の公表資料1)によると、保育士の平均給与月額は約21.6万円(平均年齢34.8歳、勤続年数7.6年)で、平均年収は約332.5万円。都道府県によって、また公立・私立によって給与は大きく異なりますが、総じて保育士の給与は低く、数ある職業の中でもワーストクラスの水準となっています。
都道府県別にみると、和歌山県の382万円が最も高く、次いで愛知県の372万円、東京都の369万円ですが、いずれも全職業の平均年収(約480万円)に遠く及ばず、最も低い佐賀県では、220万円しか支給されていません。(詳しくは「保育士の年収&ボーナス|男女別・年齢別・都道府県別における比較」をご覧ください。)
現状、保育士資格を有していながら保育士として就業していない潜在保育士数は76万人以上2)にものぼり、給与と労働のバランスが全くとれていないことが、高い離職率(低い定着率)の大きな要因となっています。
また、公立・私立ならびに認可・無認可を含め、総体的な保育園の施設数が不足していることから、待機児童が急速に増加しています。
2、政府が提示した給与引き上げ案
保育士の人材確保と待機児童問題の解消に取り組むべく、2016年4月26日に開かれた政府の1億総活躍国民会議において、安倍晋三首相は「保育士と介護士については、競合他産業との賃金差がなくなるよう処遇改善を行う」とし、同年6月2日に閣議決定したニッポン1億総活躍プランに、保育士の給与(月給)を2017年から2%(約6000円)引き上げるという処遇改善策を盛り込みました。また、経験を積んだベテラン保育士に対しては、月給4万円程度を手当するとしています。
公立保育園で働く公務員保育士となると、東京都練馬区3)の場合には、平均給与月額が33.1万円、平均年収が630.8万円で十分な給与を得ている反面、私立で働く一般保育士においては、全体の平均給与月額21.6万円、平均年収332.5万円を下回ることが通常であるため、私立で働く一般保育士にとっては特に、政府の2%引き上げ策はやる気の向上に繋がるはずです。
また、保育園の総数25580棟4)(認定こども園など含む)のうち、公立が9091棟(割合:35.5%)、私立が16489棟(割合:64.5%)と、私立の方が圧倒的に多く、それに伴い、私立で働く保育士数が多いことから、少額ではあるものの、給与の見直しが行われることに対して、多くの保育士が好意的な気持ちを持っているのが実情です。
しかしながら、この処遇改善策は未だ検討段階にあり、実施される可能性は高いものの、2017年開始となるかは疑問の渦中にあります。また、たとえ2%引き上げられたとしても、保育士の平均年収は全職業のそれに遠く及ぶわけではなく、さらに依然として労働条件に見合わないために、2%では少なすぎるという声も多く挙がっています。
加えて、2%のみでは保育士の離職率の低下(定着率の向上)に大きく影響することは考えられにくく、そもそもこの処遇改善策は経験を積んだベテラン保育士を特に優遇する処置であるため、新規就職者数の増加はさらに考えにくいということが問題点となっています。
3、待機児童の解消へ向けたその他の対策案
現在、待機児童問題が深刻になっていますが、この背景には世帯所得金額の減少が大きく関係しています。国民生活基礎調査の概況5)によると、平成26年における世帯所得金額は541.9万円。近30年では、1994年の664.2万円が最も高く、年々、世帯所得金額は減少している状態です。
子供の託児所には、大きく分けて保育園と幼稚園がありますが、一般的に幼稚園の方が保育料が高く、幼稚園の総数は保育園よりも少ないために、保護者の多くが子供の託児所として保育園を選択しています。
また、保育園では運営基準として、保育士と園児の人数配置が定められているため、保育士が不足している園では、規定以上の園児を保育することができません。さらに、特に都市部においては、商業施設や企業など、さまざまな施設が密集しており、騒音問題なども相まって、容易に保育園を増設することができません。
このように、世帯所得金額の減少に伴う保育園の選択傾向、規定の人数配置、増設の困難など、さまざまな要因が相互に絡み合い、待機児童が急速に増加しています。
中でも東京都の待機児童問題は深刻であり、保育園・幼稚園に通えず、そのまま小学校に入学するというケースは少なくありません。これを受けて、小池東京都知事は、待機児童問題におけるさまざまな対策案を表明、2016年9月9日に行われた記者会見後に政府要望を提出しました。
小池東京都知事が表明した具体的な施策は、①整備費の補助を行う(開園時の負担減)、②賃貸物件を借りている保育所に対して賃貸料の補助を行う、③宿舎・寮の借り上げ支援を採用後5年から全員に拡大する(保育士人材の確保のため)、④都有地を活用・拡大する(保育所増設のため)、⑤認可・無認可保育園の保育料の差額を埋める、⑥無認可小規模保育園の年齢規定を2年から全年齢対応にする、などがあります。
政府の給与2%引き上げ策と同様、これらは検討段階であり、必ずしも今後実施されるとは限りませんが、東京都をはじめ、さまざまな都道府県で待機児童問題に取り組む動きがみられている事実は、高く評価できると言えるでしょう。
なお、平成26年度における待機児童数6)は全国で43,184人。都道府県別にみると、最も多いのが東京都の8,672人、次いで沖縄県の1,721人、千葉県の889人、神奈川県の880人、埼玉県の658人となっており、特に沖縄県は在住の総児童数に対する待機児童数の割合が高いため、47都道府県の中で待機児童問題は最も深刻なものとなっています。
4、保育士の給与の底上げが難しい理由
上述のように、政府ならびに各都道府県・市町村が、保育士の人材確保や待機児童問題の解消を図る取り組みを行おうと動き出していますが、そもそもなぜ保育士の給与は数ある職業の中でも低水準に位置しているのかご存知でしょうか。
まず、保育園というのは主に「公立」と「私立」があり、その中でも「認可」と「無認可」の施設形態が存在します。「公立」は自治体(市町村)が運営する保育園のことで、対して「私立」は社会福祉法人をはじめとする民間団体が運営する保育園のことを指します。
さらに、「認可」とは児童福祉法で定められた認可基準を満たしている保育園のことで、対して「無認可」は認可基準を満たしてない保育園のことを指します。
認定基準には、園児の保育を円滑かつ安全に行うための基準、たとえば施設の広さや保育士等の職員数、給食設備、防災・衛生管理などの“設置基準”が設けられており、公立ではすべてが認可されているのに対して、私立は認可・無認可の両方の形態が存在しています。
保育園の主な運営費(収益)は、自治体の補助金と保育料の2つであり、認可保育園の場合には多くの補助金が支給される一方、無認可保育園の場合には補助金がゼロまたは少額支給が一般的です。
また、保育料は主に保護者の世帯所得を基に算出するという制度が存在するため、保育園ごとに独自の保育料を設定するのが難しく、さらに質の高い保育を提供する上で人員の確保が必須となるため、保育園の大半がギリギリの運営を強いられています。
このように、世帯所得に応じた保育料の算定方法や十分な人員の確保などの観点から、保育園の運営はどこもギリギリの状態にあり、保育士の給与はこの限られた運営費から支払われるため、現状ではどうしても多くの給与を保育士に分配することができず、これが低給与の大きな要因となっているのです。
保育士の給与を大きく底上げるとなると、保育士に対する直接的な処遇改善(例:政府による2%引き上げ策)のほか、自治体が負担する補助金の増額、保育料の算定方法の見直し(民営化の推進)など、さまざまな施策が必要になってきます。
また、待機児童問題にも目を向ける必要があるため、これらの施策に加え、保育園の増設や人員確保を行うとなると、必然と国や自治体の負担額は増え、財政が大きく圧迫されます。このような理由により、さまざまな要素が絡み合い切迫した現状では、保育士の給与の底上げを簡単に行うことができないのです。
(なお、保育士の低給与問題については、「保育士の低給料・重労働の実態と待遇改善に向けた国の取り組み」に詳しく記載していますので、お時間があればぜひお読みください。)
まとめ
保育士の平均給与月額は21.6万円、平均年収は約332.5万円で、多くの保育士が十分な給与を得られておらず、また保育士は長時間かつ労働を強いられることが多いため、給与と労働のバランスがとれていないのが現状です。
このことが高い離職率(低い定着率)に大きく起因しており、離職率は10%以上4)、保育士資格を有していながら保育士として就業していない潜在保育士は、およそ76万人以上2)にのぼると言われています。
このことを受けて、政府や自治体は保育士の給与引き上げ、ならびに定着率の向上のための取り組みを表明しており、特に保育士の給与については少額でも上昇する可能性が非常に高く、今後の展開に期待が持てます。しかしながら、大きく引き上げるためには、さまざまな施策を講じる必要があるため、5年先、10年先においても、保育士の大きな給与の上昇は考えにくいと言えるでしょう。
参考資料
2)社会福祉施設等調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 平成25年
3)平成26年度 練馬区人事行政の運営等の状況の公表 練馬区総務部職員課
こちらの記事もおすすめ
-
 まなぶ
まなぶ
-
親としてはこどものために、こどもが立派に育って欲しい、回りから愛される人になって欲しい、結婚
-
 まなぶ
まなぶ
-
保育園の食育のねらい|指導案と遊び、教材としてのペープサート
食育とは食を営む力を育む事です。食べる事は生きる事につながっているという考えの元、ただ出され
-
 あそび
あそび
-
歌と保育|保育園や幼稚園の年少・年中・年長に人気の歌遊び22選
歌を歌ったり聴いたりして励まされた経験は誰にでもあるのではないかと考えます。それは子どもも同
-
 お役立ち
お役立ち
-
保育士試験|筆記試験・実技試験の内容・科目と申し込み手続きの概要
保育士資格を取得するための手段の一つである「保育士試験」。受験者には保育士を志望する学生の他










