乳幼児保育とは|保育士に求められる乳幼児保育と乳児へのミルク(2017/04/06)

乳幼児保育は、近年共働きの家庭が増加していく中でもはや子育てには必要不可欠なものになりました。大切な成長過程を園で過ごす子どもたちに、保育士はどのようなことに配慮して保育を行っていけばよいのでしょう。保育に対する理解を深めるために、こちらで乳児幼児保育について詳しくご紹介します。
目次
1、乳幼児保育とは
乳幼児保育は、0歳から小学校就学までの子どもの保育をすることをいいます。乳幼児期は、子どもにとって心身ともに重要な発達がみられる時期でもありますが、父母が共に働く場合の多くは保育所に預けることが必要になります。親にかわって、幼い子どもの健康を守るとともに、成長や発達を支えていくことが乳幼児保育では大切なのです。「保育所保育指針」では、この時期の子どもの保育がいかに重要性かを述べています。
保育所は、乳幼児が、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごすところである。保育所における保育の基本は、家庭や地域社会と連携を図り、保護者の協力の下に家庭養育の補完を行い、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発達を図るところにある。
1-1、乳幼児を保育する「保育士」に求められること
保育所で乳幼児を保育する保育士には、どのようなことが求められるのでしょうか。保育士の仕事は、ただ子どもを預かることだけではありません。保育において、子どもの成長や発達に対する知識や援助にあたる技術、さらには子どもやその保護者をあたたかく包み込む人間性も求められます。この時期の子ども一人ひとりにかかわる保育士の責任はとても大きく、常に高い意識をもって務めることが求められます。保育士の「専門性」というのは、「保育所保育指針」をみると、
①子どもの発達に関する専門的知識を基に子どもの育ちを見通し,その成長・発達を援助する技術,②子どもの発達過程や意欲を踏まえ,子ども自らが生活していく力を細やかに助ける生活援助の知識・技術,③保育所内外の空間や物的環境,様々な遊具や素材,自然環境や人的環境を生かし,保育の環境を構成していく技術,④子どもの経験や興味・関心を踏まえ,様々な遊びを豊かに展開していくための知識・技術,⑤子ども同士の関わりや子どもと保護者の関わりなどを見守り,その気持ちに寄り添いながら適宜必要な援助をしていく関係構築の知識・技術,⑥保護者等への相談・助言に関する知識・技術
とあります。あらゆる可能性や個性をもつ子どもに対する保育を行うにあたり、保育士には幅広い専門的な能力の追求が必要なのです。
1-2、保育園での乳幼児保育の例「乳児への保育(ミルク)」
乳幼児の乳児は0歳、幼児は1歳からの子どもを示しています。この2つのうち、乳児への保育は、いわゆる保育士の専門性が特に問われる部分といえます。0歳児は、まだ母親の援助なしでは生きていくことができません。その母親にかわって保育を行う保育士は、乳児にとってとても大きな存在になるのです。
特に、乳児の生命を維持するために必要なミルクの時間は、今後子どもの成長や食事習慣にかかわります。保育士は、園の方針に合わせながら、乳児一人ひとりのミルクの時間を把握しておかなければなりません。さらには、その子の発達状況に応じ、保護者と相談しながらミルクの量を調整していくのも保育士の役割です。このように、保育士は得てきた知識や技術を参考に、乳児に最適な環境を整え保育をしています。
また、乳児の保育をするにあたり重要になるのが保護者とのコミュニケーション。ミルクの量や離乳食への以降、健康状態や発達状況など、細かなことを話し合いながら連携を図っていくことも、より良い保育を行うための保育士の大切な仕事になります。以下の事例は、東内瑠里子氏の「保育における「共同」の思想と保育内容の展開」から保育士が保護者に対し、乳児の食事習慣を見直すよう働きかけているものです。
保育者は、第二回クラス懇談会において、0歳児の発達の特徴と日常の姿について、日頃の子どもの姿のビデオ記録を見ながら話し合う中で、食事の量を与えることばかりを考えるのではなく、一日の生活習慣を見直すことの大切さを伝えていった。この結果、家庭では、乳汁栄養の量が減ったため、A児の食事量がかなり増えていく。また、A児、B児とも夜中は一週間ほど、ミルク欲しさにぐずっていたが、その後、ぐっすり眠ることができるようになっていったのである。
2、乳幼児保育研究所とは
「乳幼児保育研究所」という団体をご存知ですか?阿部直美氏、中谷真弓氏、そして浅野ななみ氏の3人の講師を中心とし、0歳から小学校就学までの乳幼児の発達や遊びについて研究しています。ここで、その内容を少し覗いてみましょう。
2-1、音楽リズム
乳幼児保育研究所は、保育での音楽活動に大きな力を注いでいます。手・指あそびやリズムダンス、そしてオペレッタなどの作品作りをはじめ、NHKやベネッセコーポレーションなどへの作品提供や音楽監修を行っています。ここで、乳幼児保育研究所の作品をいくつかご紹介しましょう。
「でこやまでこちゃん」は0、1、2歳児を対象としたオリジナルのうたあそびが盛り込まれています。簡単な手あそびやふれあいあそびに使える音楽もたくさんあるので、運動会の乳児クラスの親子ダンスにも役立ちそうです。
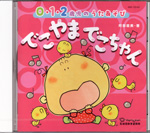
出典:乳幼児保育研究所
CDの中には、食育をテーマにしたものもあります。「ピーマンマンの食育ソング」は、「好き嫌い」や「歯磨き」、食前の手洗いなど、食事に関係する習慣の基本をうたで身につけることができます。給食の時間の前にみんなで歌ってみてはいかがですか?

出典:乳幼児保育研究所(世界文化社|2011)
年齢が大きなクラスになってくると、発表会などでうたや踊りをしながら演じるオペレッタをする園も多くなります。乳幼児保育研究所では、あらゆる物語のオペレッタを用意しています。劇に含まれているセリフやうたは簡単で覚えやすいので、発表会のネタに困ったときはここで探してみましょう。
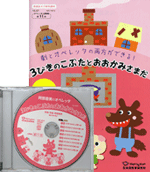
出典:乳幼児保育研究所
2-2、童話の創作と発展
乳幼児保育研究所では、数多くの絵本も出版しています。乳児を対象とした赤ちゃん絵本から幼児も楽しめるオリジナルのものまでバリエーションはさまざまです。また、絵本の読み聞かせからオペレッタへ発展させる指導法も提唱しています。子どもに劇をどのように教えていけばよいのか悩んでいたら、まずは絵本を手にとってみましょう。
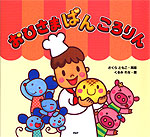
出典:乳幼児保育研究所(PHP研究所|さくらともこ|2008/07)
2-3、エプロンシアター
保育の現場で大活躍するエプロンシアター。基本の演じ方や楽しく手作りできる参考書などもこちらで販売されています。保育のネタに困ったときは、このエプロン一つ持っていれば楽しい時間になること間違いなしです。
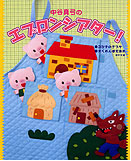
出典:乳幼児保育研究所(チャイルド本社)
2-4、セミナー
乳幼児保育研究所では、これらの教材を使った保育のセミナーを行っています。どのように絵本の読み聞かせをすればよいのか、エプロンシアターの活用法、さらにオペレッタの指導法などを実際に演じながらわかりやすく指導してくれます。早速保育現場で試せる内容なので、機会があったら参加してみましょう。
3、乳幼児保育学会とは
3-1、日本保育学会について
日本保育学会は、昭和23年に日本総合愛育研究所内(日本子ども家庭総合研究所)で設立されました。乳幼児の健やかな成長のために、保育現場と研究者が協力する場となっています。会員は、保育にかかわる約5000人、年に1回会員による研究発表大会も開催されています。日々変化していく子どもを取り巻く環境に柔軟に対応していくためにも、日本保育学会はより良い保育を追求しています。
日本保育学会は、乳幼児の健やかな成長のために、保育の実践者と研究者が協力する場です。会員は約5,000人で、教育学・心理学・福祉学の分野の学会の中では会員数の多い学会です。会員は、大学・短期大学などで保育学、乳幼児心理学、保育内容など保育・乳幼児について教授研究している人、幼稚園・保育所などで乳幼児の保育を実践している人が多く、そのほか、医師、教育相談所・児童相談所などで子育て相談に当たっている人など多様です。
3-2、日本乳幼児教育学会について
日本乳幼児教育学会は、乳幼児にかかわる多方面からの研究や乳幼児教育の振興への協力をしていく学会です。年に1回学会大会が開催されるほか、機関誌の発行など乳幼児教育の発展のために精力的に活動しています。ホームページには、学会の目的として
本学会は、急速に変化しつつある社会および国際社会の中で、乳児・幼児に関わる教育学、心理学、教育内容、教育制度などを学問的視座にたって研究を深め、相互の交流と協力を促進し、学際的、国際的、総合的研究の発展と、それによる日本の乳幼児教育の振興に寄与することを目的としています。(引用:日本乳幼児教育学会)
とあります。
まとめ
乳幼児を取り巻く保育環境は、園だけでなくさまざまな機関によって日々変化していきます。その変化に柔軟に対応しなければならないのが現場で保育にかかわる保育士。一人ひとりの子どもを把握するだけでなく、研修や講演などに足を運び、より良い保育を追求する努力も重ねていきましょう。
参考文献
保育における「共同」の思想と保育内容の展開(九州大学大学院教育学コース|東内瑠里子|2005)
こちらの記事もおすすめ
-
 行事
行事
-
行事と保育|七夕、節分、ひな祭りなど保育園のおすすめ行事3選
保育園行事は小学校や中学校と比較するととても多く、保育士は行事から行事へと日々追われています
-
 あそび
あそび
-
ペープサート|自己紹介など保育で使えるペープサートの簡単な作り方
数ある保育教材の中でも比較的取り入れやすいペープサート。通常の保育以外でも行事やイベントの時
-
 お役立ち
お役立ち
-
体操と保育|運動会で使える!親子・音楽体操など人気の体操動画5選
保育園では運動会を始め、朝の会、発表会などで体操を行うことが多くあるかと思います。何故、保育
-
 あそび
あそび
-
クイズ・なぞなぞ|謝恩会、出し物で簡単にできる動物シルエット
保育のあらゆる現場で活躍する「クイズ」や「なぞなぞ」。松本和美氏の「幼児期における文字への気










