障害児保育|歴史と事例、問題・課題・現状をふまえた研修案や指導案(2017/03/24)

保護者の方が仕事をしているなど家庭の事情で障害を抱える子どもを保育園などで預かることがあります。障害児保育とは何かを歴史的観点から見ていき、現状抱える問題点などをまとめました。障害児保育に携わる方、もしくはこれから目指そうとする方は是非参考にしてみてください。
目次
1、障害児保育とは
障害を抱える子どもを預かる場合、その子の抱える障害の状況によってどの施設で預かるかが決まってきます。障害児専門の障害児通所支援サービスの施設に通うか、保育園などの保育施設で障害を抱える子どもを受け入れているところが選択肢となります。障害児通所支援サービスは、6歳以下の子どもであれば、福祉型自動発達支援センターか医療型自動発達支援センターに分かれます。その違いは、福祉型は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの内容が中心になってくるのに対し、医療型は上肢、下肢または体幹の機能に障害を持つ子どもが利用すると区分されています。
1-1、障害児保育の事例
障害児保育の事例としては、群馬県総合教育センターによる「就学前のぐんまの子ども はぐくみガイド」の中の特別な支援が必要な子どもへの保育の項目が参考になります。
ガイドの中で、保育者は子どもの障害名にとらわれることなく、その子の特性を見極め、保育園で落ち着いて生活をしていけるような個別の指導計画を長期的な視点で作成していくことを推奨しています。特別な支援が必要な子どもは保育園全体で把握して支えていけるような体制を整え、保護者とのコミュニケーションも密にします。そして、集団の一人として生活していけるように、まわりの子どもと共に生活し成長していけるような保育を目指していくべきだとしています。
1-2、障害児保育の歴史
1974年に厚生労働省によって、障害児保育事業が始まり、全国の地方自治体で保育園での障害児保育が施策されはじめました。同時に幼稚園でも私立幼稚園特殊教育費補助事業を開始し、障害児保育の施策が始まりました。
その後改正などを重ね現在は2007年に制定された「保育対策等促進事業の実施について」に基づいて行われています。保育対策等促進事業とは、地域における保育需要に対応するために複数の省庁が合同で少子化対策に取り組む姿勢を示した、いわゆるエンゼルプラン(1994年文部・厚生・労働・建設4大臣合意)および新エンゼルプラン(1999年大蔵・ 文部・厚生・労働・建設・自治6大臣合意)等を踏まえた事業で、必要なときに利用できる多様な保育サービスの整備などの施策を総合的に展開するために定められた保育所が行う事業のことを指します。
そして、2005年に制定された新新エンゼルプランとも呼ばれる子ども・子育て応援プラン(引用元:厚生労働省)の目指すべき社会の姿の項目の中で、「障害のある子どもの育ちを支援し、一人ひとりの適正に応じた社会的・職業的な自立が促進される」という展望が記載されています。
2、障害児保育の問題・課題・現状
障害児保育の問題・課題・現状を挙げると、施設の受け入れ状況と保護者の求める形が合致しないという問題があります。障害を持つ子どもが整った環境の中、充分な保育サービスを受けられるという状況で、安心して保護者が働きに出られるような体制が整うことが求められてきます。
また、統合保育を行っている保育園では保育士の知識が充分ではないケースもあり、保育士のスキルアップも課題となります。
更に「障害児保育の歩みとこれからの障害児保育実践に向けて」(引用元:愛知教育大学・幼児教育研究の論文)では、保育者と保護者との子どもに対する認識の差を挙げています。論文によると、保育者が「気になる」と思う要素があっても、7割の保護者はそれに気づいていないもしくは問題視していないと言います。その原因は、「個性」と捉えるか、「気になる」と捉えるかの認知の差が挙げられます。そうした中で、保護者との信頼関係を壊してしまわないよう留意しながら、障害について受容出来るかどうかを見極め、伝えていく必要があると言います。
2-1、障害児保育の加配
保育園などで障害を抱える子どもを預かる場合、加配保育士をつけることがあります。
その基準などは市町村、保育園、障害の程度などにより異なってきますが、「障害児3人に対し保育士1人」が一般的となっています。障害が重度の場合は1対1の保育となる場合もあります。
療育手帳を持っている子どもに対して加配することが通常ですが、保護者は障害を抱えていると気づいていないもしくは認めていないけれど、実際には他の子どもたちに危害を加えてしまったり集団生活が全く出来ないなどの理由から保育園側の判断で加配をしているというケースもあります。
補助保育士と加配保育士の違いですが、補助保育士はあくまで担任の補助の役割を果たす目的ですが、加配保育士は何らかの問題を抱える対象児にあてがわれている保育士となるので、基本的には対象児の保育を担当するという役割となります。
3、障害児保育の仕事
障害児保育の仕事内容について、2014年に杉並区に誕生した初の障害児を専門として扱う障害児保育園ヘレンを参考に見ていきます。
基本的な仕事内容は保育園で他の子どもたちを預かるのと同様に一日の生活の流れがあり、その介助などをしていきます。その上で一人ひとりの障害の状態を把握して遊びなどを通じて発達を促していきます。また、障害を抱える子どもを持つ保護者の相談役にもなり、家庭で出来るケアなどの情報を伝えていくのも役割です。
障害を抱える子どもを保育士だけで見るのではなく、看護師・理学療法士・作業療法士などの医療職とも連携を図り子どもの発達をサポートしていきます。
また、障害児保育園ヘレンでは、医療的ケアと長時間保育を両立する預け先を増やすことを目標として保護者が安心して子どもを預けて働くことの出来る環境づくりに取り組んでいます。
3-1、障害児保育の志望動機
障害児保育を志す動機は様々かと思いますが、障害を抱える方が身近にいたり、ボランティア経験があり障害児の支援に携われる仕事を目指したなどが多いでしょうか。
採用側が注目するポイントは、志望動機が前向きな理由からか、希望する保育園の方針などと合っているか、経験やスキルが今後の仕事と結びつくかなどを見ています。
自分の気持ちを今一度整理し明確にして、何故障害児保育を志すのかをまとめていく必要があります。その上で今まで学んできたことが今後の仕事に生かせるような専門性があるかをアピールしていくことも重要です。障害児保育を目指すのであれば、児童福祉論や社会福祉論など学んできたジャンルを履歴書に書くなどして、障害児保育との結びつきをアピールしていきましょう。
3-2、障害児保育の研修
障害児保育の研修は様々のものがありますが、代表的なものとして保育協会による障害児保育担当者研修会が毎年行われている障害児保育の研修会として挙げられます。
研修会の内容は、全国から300名の保育士が集まり午前3時間、午後3時間の研修を行います。
テーマは毎回それぞれですが発達特性や困った行動への対応方法など実践的な内容をテーマに扱い、更に遊びの紹介・疑似体験・グループワーク・ビデオ学習も研修会の中に取り入れて日々の保育にすぐに活かしていけるような盛りだくさんの内容となっているようです。
3-3、障害児保育の指導案
障害児保育の指導論文統合保育における障害児理解と援助のあり方を参考に考えていきます。
障害児保育の前提として、家庭及び専門機関との連携を図りながら、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促すと共に、障害の種類、程度に応じて適切に配慮するということを念頭に、ありのままの姿を受け止めながら対象児の発達を促すような保育を意識して、様々な体験を共にして「生きる力」を培っていくことが必要とされます。それらを踏まえての指導案として、保育園の全体行事でゲームをしたり、豆まきや芋掘りなど、そういった機会がある時に保育士が援助に入りながら他の子どもたちと共に目標を達成する喜びを体験してもらいます。みんなと一緒に成し遂げるといった経験が集団の中で生活していくということを学ぶきっかけとなっていくのではないでしょうか。
3-4、障害児保育の遊び方
感覚統合という言葉がありますが、感覚からの刺激を脳で考えて、行動を決めることを指します。その感覚統合が障害を抱える子はうまく行えないといいます。そういった感覚が偏った子どもの為に遊びや運動などで感覚を正しく働きかけるようにしていくことが発達の助けとなっていきます。ここでは具体的にどのような遊びをしたらいいのかを考えるときに参考になりそうな本を紹介します。

子どもが喜ぶ感覚運動あそび40選 障害の重い子のために(出典元:福村出版|2006/6/20)
40の具体例と実践の中から獲得した知識がまとめられています。
障害の重い子のためにと題されていますが、障害の有無関係なく幼少期の子ども全般に使えそうな子どもの喜ぶあそびネタが収録されているので、障害児保育だけに限定することなく幅広く使用することが出来そうな一冊となっています。
4、障害児保育についての本
最後に障害児保育について書かれた本を紹介していきます。

障害児保育 子どもとともに成長する保育者を目指して(出典元:萌文書林|2015/4/1)
障害とは何か、発達とはどのように進むのかをやさしくまとめた、支援を必要とする子どもを理解するための知識を豊かな事例を織り交ぜて解説した一冊となっています。障害児保育に携わる人、これから目指していく人にとって必携の本です。
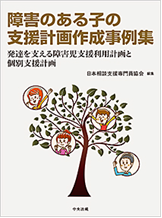
障害のある子の支援計画作成事例集発達を支える障害児支援利用計画と個別支援計画(中央法規|2016/2/20)
個別支援計画を作成していく際に、事例を参考に活用していくことが出来るので、障害児保育の指導案作成に慣れていない保育士の方に実用的な一冊と言えます。
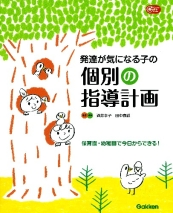
発達が気になる子の個別の指導計画(出典元:Gakken保育Books|2013/7/12)
保育園や幼稚園で作成に苦慮しているとされる個別の指導計画について具体的な記入方法やそれを使った指導実践例など現場にありがちなケースをもとにわかりやすく解説しています。
まとめ
障害児保育とは何かから始まり、指導案などについてまとめてきました。
障害を抱える子どもの保育は、通常の保育以上にその子の特性を見極め、発達の助けとなるよう援助をしていく必要があります。ですが、目指していくところは同じであり、保育園を卒園し、小学校へと進学していく先まで長期的に見通しを立てて、集団の中で生活していく習慣を身に付け社会の一員として生活していけるような基盤を作っていくというところが保育園での役割ではないでしょうか。障害を抱える子どものありのままの姿を受け止めながら、苦手としているところに寄り添い発達の助けとなっていけるよう保育者は、自分の持つ専門的な知識を活かし、対象児やその保護者と関わっていく必要があります。
こちらの記事もおすすめ
-
 お役立ち
お役立ち
-
月案と保育|年齢別(0歳児、1歳児、2歳児、3歳児)の月案の立て方
保育園での生活で中心となってくるのが指導計画に基づいた保育内容です。指導計画は、年間計画から
-
 お役立ち
お役立ち
-
保育園で働く際、また保育実習で保育園を訪れる際にも、欠かせないのが名札となります。エプロンな
-
 まなぶ
まなぶ
-
0歳児保育とはどのようなものなのでしょうか?どのような内容で保育をし、どのような姿を目指して
-
 あそび
あそび
-
フィンガーペインティングの保育のねらい|造形遊びを通して学ぶ
フィンガーペインティングとは、『できた絵を重要視するのではなく自由に感触を楽しんだり、指で絵の
-
 お役立ち
お役立ち
-
保育士の自己紹介|保育実習で使える自己紹介カード・グッズの作り方
保育園で初めて子どもたちと対面する時、最初に行うのが自己紹介となります。子どもに行う自己紹介










